皆さん、こんにちは。World Sports Pulseをご覧くださいまして、ありがとうございます。
「昔のバレーと今のバレー、別モノだよね?」と昭和世代(つまりアタシ😁)が言うと、令和世代は「は?何言ってんの?これが普通でしょ😒」と、きっちりハッキリ返してきます。
ムカつきますが、世代間の“感じ方ギャップ”は、実はルールの歴史がつくったもの。ここでは、なぜルールが変わったのかに焦点を当て、感情も交えながら丁寧にひも解いていきます。
まず結論:変化の理由は“面白くするため”と“生き残るため”
バレーボール🏐の大改革は、競技の魂を売ったのではありません。面白さを増幅し、スポーツとして生き残るための必然でした。テレビ放送との相性、試合時間の予測可能性、世界的な人気維持――この3点が、ルール変更の“母体”になっています。
昭和:15点サイドアウト制—長く、重く、尊かった時代
サーブ権があるときだけ得点できるサイドアウト制。(懐かし〜。)
1点が重く、ラリーが延びるほど価値が増していたのでしょうか。まあ正直、試合は長い(でも良かった)。やっている方は必死ですが、観ている方はいつまで続くんだ〜と思ったことは1度や2度(もっとかな)はありましたよね。
1セット1時間なんてザラ、フルセットなら家族が先に寝ている――そんな時代です。
この“重さ”は確かに美しかった。けれど、テレビの編成マンとスポンサーの胃に穴が空いたのも事実です(比喩ですよ、比喩)。
ちなみに私は、この時代です🥸 そしてユニフォームはブルマに長袖でした〜(笑)

写真:News ポスト
平成:ラリーポイント制へ—テンポを上げて“見える”競技に
1999年、FIVBはラリーポイント制を導入。ラリーが終われば必ずどちらかに点が入る。セットは25点になりました(最終15点)。これで平均試合時間は短縮し、放送枠に収まり、最後まで目が離せない競技に変わりました。
昭和世代の私も最初は抵抗がありました。「味が薄まるんじゃね…?」「ちっとも面白くないやんけ」と。けれど、毎ラリーが点に直結する緊張は“別種の旨味”でした。今ではそれがテンポが良く、視聴者が入りやすいから面白いモンです。スポーツとしての“門戸”が広がったのでしょう。

写真:日刊スポーツ
リベロ誕生(1998):守備のプロが物語をつくる
背番号もユニフォームも違う、守備専任のリベロ。初めて聞いた時には、「何それ?」と思ったものです。日本の粘り文化に合致するこのポジションは、拾って、つないで、流れを変える。
リベロの1本がハイライトになる時代を、誰が想像したでしょう。リベロとはイタリア語で「自由libero」という意味だそうです。守備でも、どこでも戦えるポジションを指す言葉だとか。サッカーでも使われている言葉ですよね。
「背は低くても世界で戦える」――子どもたちの夢の入口が増えたことの価値は、メダルに換算できません。


写真:日刊スポーツ
比較でわかる、何がどう変わった?
| 項目 | 昭和(旧) | 平成以降(新) |
|---|---|---|
| 得点方式 | サイドアウト制(サーブ権時のみ得点) | ラリーポイント制(毎ラリーで得点) |
| セット | 15点先取(デュース多発) | 25点先取(最終15点) |
| 試合時間 | 読めない(長い) | 概ね読める(放送向き) |
| 戦術の重心 | サーブ権管理・根気勝負 | サーブで崩し、早い展開で刺す |
| スターの多様性 | 高さ・火力に偏りがち | リベロなど役割特化が主役になれる |
「なぜ」の核心:スポーツとメディアの共存
オリンピック種目であり続けるには、“観られるスポーツ”である必要がある。観られれば競技人口が増え、スポンサーがつき、強化に資金が回る。逆に観られなければ、いずれ競技の未来は痩せてしまう。
ルール変更は、伝統の否定ではありませぬ。伝統を未来へ運ぶ船🚢💨だったので〜す。
今:日本代表が“全員バレー”で世界と殴り合える理由
高さで不利でも、スピードと多彩さで勝負できるのは、ラリーポイント制と役割最適化(リベロ等)があってこそ。
男子は組織的攻撃とサーブの設計で世界へ肉薄。女子はレセプションの安定と速いコンビで巨塔を揺らす。昭和〜平成の“変化の果実”を、令和の代表がもぎ取っているのです。
高さと言えば・・・知ってますか、アタックを打つ時の到達点を。googleで検索すると、イタリア🇮🇹とアメリカ🇺🇸のの2人が出てきました。
日本人🇯🇵では、和田由紀子選手が293cm、長岡望悠選手が310cmの最高到達点を記録しており、トップレベルの跳躍力を誇っています。
長岡選手が引退を発表してとても悲しい😭。ショートヘアの時の彼女がとてもカッコよかったのですよ。身体の伸びというか、ジャンプ力が本当にすごかった😍とにかくとにかくカッコよかったの一言に尽きます。
街中を走っているバス🚌の高さが350cmだとか。どんだけ飛んでいるのか分かりますよね?
パオラ・エゴヌ(イタリア):344cm
フォルケ・アキンラデウォ(アメリカ):331cm
まとめ:変わったのはルール、変わらないのは熱
サイドアウトの重みを知る人も、ラリーポイントのスリルで育った人も。どちらの胸にも同じ鼓動がある――最後の1点が入る瞬間の、あの息を呑む静けさ。ルールは時代に合わせて姿を変えましたが、観る私たちの熱は、何も変わっていません。
今日もボールは床と床のあいだで、物語を描き続けます。(ちょっとカッコつけてみました😎)
関連記事:
・男子バレー日本代表、ブルガリア快勝の裏に隠された「3つの意味」
・世界バレー2025完全ガイド(日程・放送・見どころ)
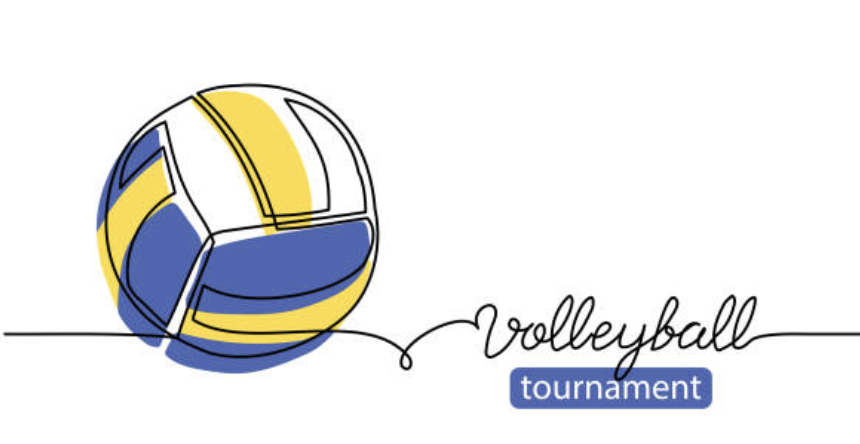

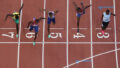
コメント